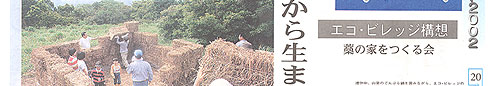|
【報道記事】
「藁の家」と言っても童話「三匹の子ぶた」でオオカミにふきとばされたようなちゃちな家じゃない。わらを固めたブロック製で、多少の雨風ではびくともしない。シックハウス症候群などとは無縁の天然素材を使用、壊した後は土に還り循環型社会にぴったり。こんな優れものの家づくりが、佐賀県山内町で市民グループの手で進んでいる。五月晴れのある日、現場を訪ね、家づくりに参加した。
佐賀市から西に30キロ、長崎県波佐見町境の神六山のふもとで家づくりは進んでいる。建てているのは「藁の家をつくる会」=山田信行会長のメンバー。月1回の作業で、地ならしや基礎工事は終わり、この日から、わらを固めたブロック「ベイル」(幅75センチ、奥行き30センチ、厚さ40センチ)を積む作業が始まった。
藁の家を思い立ったのは会長の山田さん。1級建築士として仕事をする中、接着剤や建材の防腐剤などに化学物質が使われ、シックハウス症候群が問題となる家づくりに疑問を持った。「心地よい家をつくってみたい」。調べるうちに、目にとまったのがわらの家だった。米国ではストローベイルハウスとよばれ、実際に住んでいる人もいるという。「これなら人にも自然にも優しい」。山田さんの呼びかけに、建築会社社長や測量士、左官など、約30人が集まった。
作業は、昨年秋、建設現場のススキを刈り取ることから始まった。1、2月に天日に干して乾燥させ、干し草を作る機械で固めた。ベイルは重さ約10キロだが、積み上げ作業は楽ではない。家は幅4.4メートル、奥行き3.6メートル。5段に積み上げるのには100個のベイルが必要だ。初夏の日差しに焼かれながら、両手でベイルを抱えて何度も運ぶ。傍らでは、子どもたちが積み上がったベイルのすき間を、石灰やわらを混ぜて作った泥で塗り固めていく。
福岡県筑紫野市から通う測量士の谷口敏之さんは「ここにくると童心に帰る。8月には初めての子どもが産まれるが、いつかこんな作業を一緒にやれたら最高」。
建築のプロたちが、積み上げたベイルがきちんと水平になっているかチェックする。こっちには、竹割りの作業が回ってきた。等間隔に竹の棒を立て、ベイルをひもで結んで固定するのだ。ナタで縦に4分割するのだが、刃がひっかかってうまくいかない。「『木元、竹裏』といって、竹は頭から刃を入れるんだよ」。教えてくれた男性は学校の先生だった。教えに従ってやってみると、なるほどすーっと小気味よく割れていく。
この日の作業を終え中に入ると、8畳ほどの広さ。何か柔らかいものに包まれている感じで、住み心地がよさそう。7月の完成が待ち遠しい。
|